■すばらしい新世界 / オルダス・ハクスリ―
すべてを破壊した“九年戦争”の終結後、暴力を排除し、共生・個性・安定をスローガンとする清潔で文明的な世界が形成された。人間は受精卵の段階から選別され、5つの階級に分けられて徹底的に管理・区別されていた。あらゆる問題は消え、幸福が実現されたこの美しい世界で、孤独をかこっていた青年バーナードは、休暇で出かけた保護区で野人ジョンに出会う。すべてのディストピア小説の源流にして不朽の名作、新訳版!
先日『1984年』 を読み終わったのでついでと言ってはなんだが同じくディストピアSF小説の古典として名高いオルダス・ハクスリーの『すばらしい新世界』を読んでみることにしたのだ。
オルダス・ハクスリーは1894年イギリス生まれの作家。この『すばらしい新世界』は1932年、『1984年』刊行の17年前に出版された長編小説であり、アメリカのモダン・ライブラリーが選ぶ「英語で書かれた20世紀の小説ベスト100」では『ユリシーズ』『グレート・ギャツビー』『若い小説家の肖像』『ロリータ』に次いで第5位に選ばれた高い評価の小説なのだという。
物語は破滅戦争終結後の26世紀の未来が舞台となる。この世界では共生と安定のスローガンのもと人類初のユートピア社会が生み出されていた。人は全て試験管によって生み出され、育児・教育は一括管理され、条件付けされた人々による社会は平和そのもので、病気も老いもなく、フリーセックスと安全なドラッグにより誰もが幸福極まりない生活を営んでいた。しかしそこに保護区に住む「現世種」の青年が現れることにより新たな混乱が生み出されるのだ。
人間が皆オートメーションシステムによって生み出される。知能や身体能力は遺伝子操作により出生前に決定され、出世後はそのランクごとに階級社会が形成される。条件つけられているがゆえに人々は自由意志を持つ必要もなく、予め決定された生を何一つ疑問も持たず生きることになる。これにより社会は安定し、誰もが一見幸福そうに生きるけれども、これは本当にユートピアなのか?誕生から死まで全てが管理され条件付けられた社会、「自分で決定できる自分自身の生の無い世界」、それはディストピアなのではないのか?というのがこの『すばらしい新世界』である。
とまあこんな「全てが完全管理されたディストピア」を描いている筈の『すばらしい新世界』だが、オレには「いやこれ普通にユートピアじゃん?」と思えてしまった。妊娠出産から開放されているといった点で女性には楽園だし、育児教育は国家が行うので家族といった概念が存在せず当然結婚も存在せず、そういった部分で家族と結婚にまつわる全ての病理が存在せず、自由恋愛でフリーセックス社会だから性と男女の問題も一切存在せず、副作用の無いドラッグがやり放題なので誰もが皆精神状態が安定していて、医学の発達により病気も老いも無く、仕事は遺伝子操作により出生前から能力別にカーストが存在して、その決められた仕事をこなせば生活ができるので、就職や失業や収入についての不安も存在しない。ただし60歳になったら全員安楽死ということになっているけれど、そもそもそういう社会だから誰も疑問にも思わない。
これら「幸福の名の下に全てが管理された社会」というのは、そもそもにおいて、現在の人類社会の目標じゃないか。しかしこの物語において何が問題となっているのかといえば、それは「自分の人生を自分で決定できる自由が存在しないこと」となる。物語はここで「保護区に生きる昔ながらの出産の形で生まれた野人(現生人)」を持ち出し、自由意志を尊ぶ彼の行動と物語におけるユートピア社会とを対比させることにより、「自由意志の可否」を浮き上がらせる。野人の青年バーナードは「自由意志の為ならどんな不幸になってもいい」と豪語するけれども、自由意志など無くても誰もが幸福な社会でそんな意思など本末転倒に過ぎない。そもそも現実の社会においてさえ、自由意志などどれだけ有意なのか?実は「自由意志だと思い込める範囲の自由意志」を持たされて管理されているだけではないのか?この物語にはそういったぎりぎりのアイロニーが込められているように思う。
同じディストピア小説『1984年』と比べてどうだろう。『1984年』は人間の愚かさから生まれた地獄を描くけれども、『すばらしい新世界』は人間の公正さによって生まれた非人間的社会であるといっていいだろう。『素晴らしい新世界』の物語は『1984年』よりもはるかに合理的であるからこそよりおぞましい。文学として優れているのは『1984年』だが、SF的思考実験小説として楽しめるのは『すばらしい新世界』だといえるだろう。さらにこの物語、後半は相当にスラップスティックな展開を見せ、「ディストピア小説」といったジャンルから感じる陰鬱さがまるで無い部分が面白い。






![一九八四年[新訳版] (ハヤカワepi文庫) 一九八四年[新訳版] (ハヤカワepi文庫)](https://m.media-amazon.com/images/I/41ZAgdWin2L.jpg)
![一九八四年[新訳版] (ハヤカワepi文庫) 一九八四年[新訳版] (ハヤカワepi文庫)](https://m.media-amazon.com/images/I/41ZAgdWin2L._SL160_.jpg)


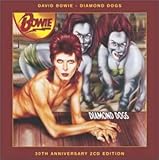
![1984 HDニューマスター版 [Blu-ray] 1984 HDニューマスター版 [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51iust9RpHL._SL160_.jpg)






