Mr.ノーバディ2 (監督:ティモ・ジャヤント 2025年アメリカ映画)

しょぼい親父を主人公とした「怒らせたヤツは殺人マシーンだった」ジャンルの第2弾。前作で過去の敵を皆殺しにしたはずのハッチ・マンセル(ボブ・オデンカーク)は、妻ビッキーと二人の子供たちとの穏やかな日常を取り戻していた。しかし、家族旅行中に再び犯罪者集団に襲われ、休暇は一転して全面戦争に。家族を守るため、ハッチは再び殺人マシーンに覚醒する。今回は家族総出で戦う、絆と破壊のアクションが炸裂する。
1作目は孤独な復讐劇の爽快無双が魅力だったが、本作は家族との関係修復をしっかり軸に据え、家族の絆が明確に描かれている点が印象的。後続ではあるがAppleTV+の『ファミリー・プラン』とかなり似たテイストで、殺し屋パパが家族を巻き込みながら守り抜く展開が重なる。家族みんなで敵を倒すシーンは、単なる無双を超えてほっこりする一体感があった。ストーリーは相当大雑把で、休暇中のトラブルから巨悪組織との戦争へ一直線。細かい伏線や意外性は薄いが、テンポが良く退屈しない。ボブ・オデンカークのコミカルで哀愁漂う演技が健在で、家族とのぎこちないやり取りが笑いを誘う。
最大の見どころはクライマックスの遊園地アクション。廃墟化した遊園地を縦横無尽に使い、観覧車、ボールプール、ミラーハウス、ウォータースライダーなどが殺人トラップに変貌する。『ホーム・アローン』をスケールアップさせたようなド派手な破壊と肉弾戦が最高に爽快で、前作の工場戦を完全に上回るカタルシスを提供する。馬鹿馬鹿しい作品だが十分に楽しむことができた。
ファミリー・プラン2(Apple TV+)(監督:サイモン・セラン・ジョーンズ 2025年アメリカ映画)

元特殊工作員のマイホームパパが、再び殺し屋モード全開で家族を守る!いつも家族に甲斐甲斐しいマイホームパパ、ダン・モーガン(マーク・ウォールバーグ)は、妻ジェシカ(ミシェル・モナハン)と子供たちとのクリスマス休暇でヨーロッパ(ロンドン中心)へ旅行に出かける。ところが、過去の敵が再び襲来。家族総出で迎え撃つ羽目になり、異国の街並みを舞台に大規模な戦いが勃発する。ダンの超人的なスキルと家族の絆が試される、笑いとアクション満載の続編だ。
前作『ファミリー・プラン』(2023年)は楽しんで観れることができたが、今作も期待通りの安心感とスケールアップが最高だった。前作はラスベガスでのバカンスが舞台で、家族を巻き込んだ痛快な戦いが魅力だったが、本作は海外旅行というワールドワイドなロケーションでダイナミックさが大幅に増している。美しいロンドンの街並みや異国情緒の中で、何が起こるか分からないサスペンスが加わり、緊張感と爽快感が倍増。家族総出による事件解決はより痛快で、みんなで協力して敵を倒すシーンは絆の強調が功を奏し、心温まる一体感があった。
マーク・ウォールバーグは「普通の父親なのに実は超人」という役が本当に似合う。コミカルな家族とのやり取りと、シリアスなアクションの切り替えが絶妙で、笑いどころも満載。Apple TV+らしい丁寧な作りで、コメディとアクションのバランスが良く、ガチャガチャしすぎず安心して観られるお茶の間映画の完成形だ。物語設定に新味はないが、前作の良さを引き継ぎつつ、海外舞台の爽快感で十分楽しめた。家族で観てほっこりスカッとしたい時に最適な一作だ。
![Mr.ノーバディ2 ブルーレイ + DVD セット [Blu-ray] Mr.ノーバディ2 ブルーレイ + DVD セット [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51FJynGsPTL._SL500_.jpg)


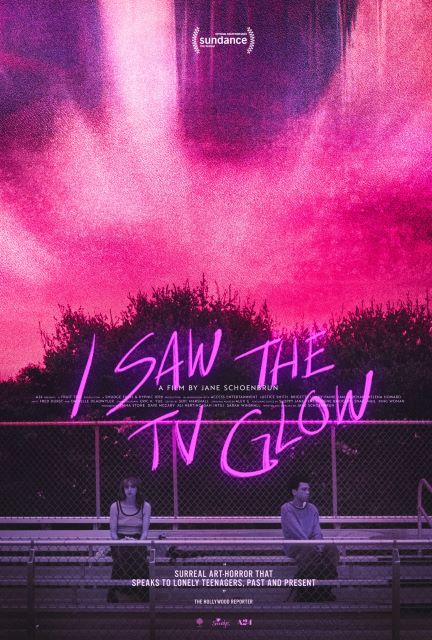

![テレビの中に入りたい [DVD] テレビの中に入りたい [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/41FRJuyrS7L._SL500_.jpg)
![【Amazon.co.jp限定】テレビの中に入りたい (L判ブロマイド4枚セット 付) [DVD] 【Amazon.co.jp限定】テレビの中に入りたい (L判ブロマイド4枚セット 付) [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/41Ufx+TTXpL._SL500_.jpg)


