■夜のみだらな鳥/ホセ・ドノソ
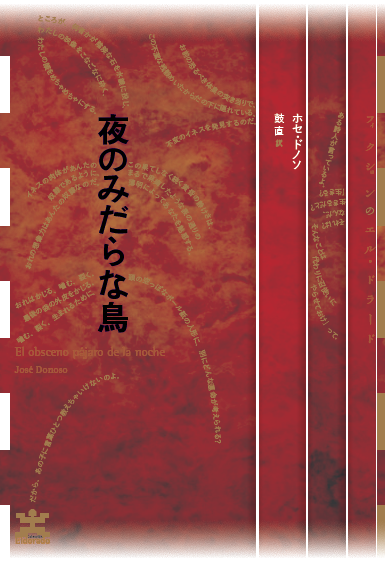
望まれない畸形児“ボーイ”の養育を託された名家の秘書ウンベルトは、宿痾の胃病で病み衰え、使用人たちが余生を過ごす修道院へと送られる。尼僧、老婆、そして孤児たちとともに暮しながら、ウンベルトは聾唖の“ムディート”の仮面をつけ、悪夢のような自身の伝記を語り始める…。延々と続く独白のなかで人格は崩壊し、自己と他者、現実と妄想、歴史と神話、論理と非論理の対立が混じり合う語りの奔流となる。『百年の孤独』と双璧をなすラテンアメリカ文学の最高傑作。
I.
「ラテンアメリカ十大小説」とも謳われるホセ・ドノソの『夜のみだらな鳥』を読んだ。
異様な物語である。解体された動物の、細切れになった肉や皮や骨や臓物がどろどろに混じり合った桶の中に手を突っ込み、それをぐちゃぐちゃとこねくり回しているかのような、忌まわしくおぞましい感触と得体の知れない混沌とが全編を覆う物語である。
いわゆる”作話”としての”物語”は一応存在する。主人公は解体が予定される打ち捨てられた修道院に住む一人の男だ。その修道院には40人にのぼるホームレスの老婆と5人の孤児が住み付いており、男はその世話役だった。そして孤児である一人の少女の処女懐妊(実は主人公の子)が描かれ、それに色めき立つ老婆たちの姿が描かれ、この修道院を管理する資産家の男とその妻との冷たい結婚生活が描かれ、この資産家の妻に対する主人公の肉欲が描かれ、やがて生まれた資産家の男の息子が畸形であったことが描かれ、その畸形の息子の為に畸形ばかりの住む楽園を作り上げてしまう資産家の妄執が描かれることになる。
II.
確かに「”作話”としての”物語”」それ自体も異様ではある。しかしこの作品の「異様さ」は、まずひとつはこれらの”描かれている事物”の時系列がぐちゃぐちゃと混ぜ合わされ明確な時間の流れが判別できない部分にある。次に三人称と一人称が混在しているばかりか、その一人称の”語り手”である筈の者が予告なく次々と遷り変り、さらにそれが事実なのか虚構なのかあるいは妄想なのか判別付かない部分にもある。さらにはその”語り手”自体が実際に存在するものなのかどうなのかすら判らなくなってくる。まるで虚構が虚構を生みその虚構が虚構を生んでいるかのような混沌と混乱をあえて描写として適用しているのだ。
小説というのはそもそも虚構であるが、虚構ではあれ時間と空間があり、その時間の流れと空間における動作(登場人物の思惑、行動)があることによって一つの世界観を構築し成り立つものであるところを、この作品においては冒頭に書いた「臓物の詰まった桶」の如く構成物全てがぐちゃぐちゃどろどろと混ざり合ってしまっている。それにより、「物語であることの前提」を引き潰し解体してしまった【物語】として提示する、ということをやってのけているのだ。時間も空間も朦朧として判別の付かない世界でどろどろと異様な出来事が描かれるこの物語は、すなわち【悪夢的】ですらある。
III.
それでは何故この作品は悪夢的な物語と崩壊した叙述法に拘ったのだろうか。この物語を読み通した時、そこから滲み出て来るものは徹底的な「自己否定」である。その「自己」とはラテンアメリカ文学に顕著な「マッチョとしての男=自己」であり、この作品ではそれを完膚なきまでに破壊し尽くそうと試みられているのだ。
まず主人公は「負け犬」として登場する。負け犬とは「男権社会において男と認められない外れ者」のことだ。主人公は作家を目指すがマッチョな父に否定され家を飛び出る(男性性との軋轢)。そんな主人公を拾ったのは「社会的成功者=男の中の男」である資産家だが、主人公は資産家と自分との対比に劣等感を抱くばかりだ(自己卑下)。やがて修道院の世話係になる主人公はそこに住み付く老婆たちと同化し自らも老婆の如き存在と化す(男性性の放棄)。
修道院で暮らす浮浪者の少女に想いを寄せる主人公は仮面を被り他人に成り済ますことで少女と性交することができる(自己存在否定)。妊娠した少女は老婆たちに処女懐妊ともてはやされる(生殖行為における男性性の排除)。子宝に恵まれない資産家の妻は主人公とまぐわい子を成そうとするが、主人公は己の男根は己のものではなく資産家のものであると妄想する(自己疎外/男根否定)。畸形の王国の管理者となった主人公は手術によって自分の肉体の各部位が畸形のものと交換されていると思いこむ(肉体の排除)。その時生殖器も置き換えられたと幻覚する(去勢恐怖/去勢願望)。さらに主人公は老婆たちの手によって御蚕包みの幼児と化す(退行)。
こうして主人公はマッチョたちの君臨する男権社会から徹底的に逃走し遁走する。自己を否定し自己の男性性を否定する。それは男になれない負け犬の男の侘しく惨めな咆哮だ。主人公のこの逃走と否定の彼方にあるものはなにか。それは女たちの支配する奇妙に歪んだ女系社会なのである。
IV.
主人公と資産家以外でこの物語で主たる登場人物となるのは殆どが女だ。物語の冒頭がまず女中の葬儀だ。そして修道院に住み付く無数の老婆の群れ。主人公が想いを寄せた浮浪者の少女。主人公が赦しを乞う時に常に呟かれる尼僧の名。修道院の権利を主張し権勢を振るう資産家の妻。畸形の王国を実質管理する小人の女。主人公はこれら女たちの世界で、全ての男性性を放棄したまま、同時に男とも認識されずに、男であることの軋轢からようやく逃れるのである。けれどもその女系社会でさえこの物語では歪なものとして描かれ、それはあたかも暗闇で生きる隠花植物の如きじとじとと湿った生の在り方なのだ。
物語はマッチョとしての男権社会を否定しそこから逃走する主人公を描きながら、主人公が逃避した女系社会すらもあさましく愍然たるものとして描く。結局、男たちの社会が肉食動物の咆哮する世界であるのと同じぐらい、女たちの社会も魍魎たちの蠢く世界でしかないということなのだ。その社会で主人公は、男でも女でもない、「見えない存在」としてしか扱われない。即ちそれは、男ではない男はただ存在できない者であるということなのだ。ホセ・ドノソの『夜のみだらな鳥』はこうして、自己否定の彼方の寂寥として荒漠たる世界を描き出してゆくのである。