DUNE/デューン 砂の惑星 (監督:ドゥニ・ヴィルヌーヴ 2021年アメリカ映画)

小説『デューン 砂の惑星』
1965年にフランク・ハーバードによって書かれたSF大河小説『デューン 砂の惑星』は当時のSF界に大いなる衝撃と絶賛でもって迎え入れられた。その評価の中心となったのはこの物語が一つの特殊な生態系を舞台とし、その生態系を迫真的に描くことよりリアリティ溢れる異世界を構築したことにあるだろう。作品はSF界の権威ある賞、ヒューゴー賞とネヴュラ賞のダブルクラウンを獲得し、今も揺るぎない評価を得続けている。
作品はその後も『デューン/砂漠の救世主』『デューン/砂丘の子供たち』『デューン/砂漠の神皇帝』『デューン/砂漠の異端者』『デューン/砂丘の大聖堂』といった続編が次々と書かれ、まさに「サーガ」に相応しい世界観を形作った。また、作者没後も息子の手によって続編が書き続けられている。
日本での翻訳刊行時は石ノ森章太郎による表紙の4巻本として発売された(現在は3巻本)。この時も日本SF界を大いに賑わせていたことをなんとなく覚えている。オレ自身が実際に小説を読んだのはデヴィッド・リンチ映画化作品公開の直前だった。舞台となる砂の惑星、「ベネ・ゲセリット」だの「クイサッツ・ハデラッハ*1」だのといった特殊な造語が独特の異世界感を醸し出し、オレも十分にハマって続編にも手を出して読んだ。
映画『デューン 砂の惑星』
映画版『デューン 砂の惑星』と言えば製作の頓挫したアレハンドロ・ホドロフスキー版『DUNE』、製作はされたが大コケしたデヴィッド・リンチ版『デューン 砂の惑星』(84)が挙げられる。これら失敗の原因はなにしろ原作が長大でややこしい造語が多く、1本の映画作品にまとめ難いという事に尽きる。
ちなみにホドロフスキー版はその後ドキュメンタリー映画『ホドロフスキーのDUNE』(13)として製作頓挫までのいきさつをまとめており、華麗なるイメージボードやプロダクトデザインも含めてこれはこれで優れた作品として仕上がっている。デヴィッド・リンチ版も歪な失敗作とはいえ、リンチらしいグロテスクなイメージが横溢するファンにとっては愛着のある作品と言えるだろう。
長々と『デューン』の来歴を書いたのは、そもそもこの作品が小説としてどれほど高く評価されたものであり、なおかつ映画化の困難な作品であったかを言いたかったからだ。1965年という50年以上前に執筆されながら幾多の映画化構想断念と映画化失敗を繰り返し、それでもなお映画化の望まれる原作小説が、本国でいかに愛され崇敬されているもののか、その一端でも知ってもらいたかった。
そしてドゥニ・ヴィルヌーヴ監督版『DUNE/デューン 砂の惑星』へ
そしていよいよ、真打とも言うべき「完全映画化作品」が登場することになる。それが今回公開されたドゥニ・ヴィルヌーヴ監督版『DUNE/デューン 砂の惑星』である。ただし「完全映画化作品」とは書いたが、ひとつだけ、これは必ず念頭に置いて欲しいが、この『DUNE/デューン 砂の惑星』は映画冒頭に『Dune: Part One』と謳われるように、2部作の第一部に過ぎない。即ちこれ1作では完結していないのだ。これから鑑賞される方はそこを注意して劇場に行かれて欲しい。
《物語》人類が地球以外の惑星に移住し、宇宙帝国を築いていた西暦1万190年、1つの惑星を1つの大領家が治める厳格な身分制度が敷かれる中、レト・アトレイデス公爵は通称デューンと呼ばれる砂漠の惑星アラキスを治めることになった。アラキスは抗老化作用を持つ香料メランジの唯一の生産地であるため、アトレイデス家に莫大な利益をもたらすはずだった。しかし、デューンに乗り込んだレト公爵を待っていたのはメランジの採掘権を持つハルコンネン家と皇帝が結託した陰謀だった。
というわけでヴィルヌーヴ版『DUNE』であるが。
これがもう、最高だった。
原作を過不足なく細やかに脚色し、じっくり確実に描いてゆくその語り口調は、原作とそのファンへの最大限の敬意を表しているだけではなく、ホドロフスキー版、リンチ版の失敗を踏まえてのものなのだ。この「じっくり描く」ことこそが『DUNE』の稀有なる世界を表出させる鍵なのだ。これを長すぎるとか端折ってしまえとかいう言説は不適格だろう。
透徹した世界観に裏打ちされた素晴らしいSFヴィジュアル
もちろん原作を丁寧になぞっただけの映画ではない。ただでさえ奔放なSFイメージに溢れた原作を、優れた想像力と美意識でもって、現在可能にし得る最高のSFヴィジュアルとして提示しているのだ。それはスペースシップや異世界における建造物、その内装ばかりではなく、登場人物の着る衣装一つ一つ、彼らの持つガジェットに至るまで、透徹した世界観でもって描き切っているのである。
即ち、『DUNE/デューン 砂の惑星』は、美しく、絢爛極まりない映像を見せつける映画なのだ。観る者はその世界の中に放り込まれ、その迫真性に没入し、陶然となりながら異質極まりない世界を闊歩することになるのだ。ヴィルヌーヴ監督はこれまで、『メッセージ』や『ブレードランナー2049』といったSF作品で素晴らしいSFヴィジュアルを見せつけてきたが、『DUNE』はその総決算ともいうべき作品となっている。
もちろん世界はただ美しいだけではない。舞台となる砂の惑星アラキスは人間の生存を拒むどこまでも厳しく荒々しい世界でもある。この死と隣り合わせの世界で、人々がどう適応し、生き抜こうとしているのかがこの物語の大きなポイントであり、大いなるドラマを生み出している点でもあるのだ。
宮廷暗黒劇と超未来科学技術の混在する宇宙世界
その優れたヴィジュアルでもって描かれる物語は、銀河の星々に遍く人類が住み着いた遠未来の宇宙帝国を舞台にした、【宮廷暗黒劇】なのである。大いなる富を生み出す砂の惑星アラキスを巡るアトレイデス家とハルコンネン家との確執、その確執を利用せんと蠢く銀河皇帝の陰謀、さらに銀河の未来を操作すべく暗躍する組織ベネ・ゲセリット。ここで語られるのは中世ヨーロッパ世界を思わせる覇権を巡る権謀術策であり、そこから生み出される血腥く腐肉の臭いすらする権力闘争なのである。
遂にバランスを失った権力構造はハルコンネン家による無慈悲な殺戮と完膚無き破壊を呼び寄せ、そしてアトレイデス家の第1子ポール・アトレイデスの復讐の予兆が胎動する。そういったある意味古色蒼然としたドラマが、煌びやかな遠未来科学技術と合体し、屍累々たる白兵戦と超未来破壊兵器が全てを蹂躙する、恐るべきSF世界を表出させるのだ。いわば『ゲーム・オブ・スローンズ』のSF版と言っていい世界なのだ。もちろん『ゲースロ』より『DUNE』のほうが先に生み出されたが。ここには古きものと新しきものとの融合がある。
過酷な環境の中で生きる人々とその信ずるもの
この【宮廷暗黒劇】を受けてもう一つ語られるのは、惑星アラキスに初期の段階に移住したフレメンと呼ばれる人々である。彼らは為政者と対立しながら砂漠に隠れ住み、過酷な環境に適応した独特の社会に生きる人々だ。彼らは戦闘能力と隠密能力に長け、その過酷な生活を救う「伝説の救世主」の到来を待っている。そして難を逃れたポール・アトレイデスは彼らとの共闘を考える。ここで描かれるのは「異文化との衝突」ということなのだ。
この図式から想像できるように、『DUNE』の物語は、現実の中東世界とそこに生きる人々、その中東世界が生み出す貴重な地下資源・石油を巡る西欧列強国家同士の牽制とが下地となっている。石油=アラキスが産出する宇宙規模に貴重な生産物メランジ、というわけだ。そこに現われる「伝説の救世主」とはポール・アトレイデスなのか否か、というのがこの物語なのだが、「中東世界に白人の救世主?」という疑問はヴィルヌーヴ監督も意識しているらしく、それは今後語られる第2部で明らかにされるはずだ。
それと同時に、ここでは単純に「中東世界」を模しているのではなく、東洋的な精神世界も加味されており、砂漠の巨獣サンドワームへの畏敬や共存の在り方も含め(これなどは動物崇拝の存在するインドやタイを連想させる)、もっと複雑な「第3世界的なるものの混淆」がこのアラキスなのではないかオレは思う。
粒揃いの俳優陣による贅沢なドラマ
こうしたドラマを演ずる俳優陣がまた素晴らしい。主人公ポール役のティモシー・シャラメは少年の線の細さと青年の力強さの狭間を繊細に演じ、父親役オスカー・アイザックは父の威厳と為政者の困難を、母親役レベッカ・ファーガソンは愛情深さと凛とした強さをしっかりと演じ切っていた。
ジェイソン・モモア、ハビエル・バルデム、ジョシュ・ブローリン、デイブ・バウティスタ、誰もがオレの好きな俳優であり誰もが素晴らしい演者だった。まさかシャーロット・ランプリングまで出演しているとは思わなかった。ヒロインのゼンデイヤは第2部での活躍を期待したい。チャン・チェンはオレはよく知らなかったのだが、今後作品を探してみたい。このような粒揃いのオールスターキャストの作品としても『DUNE』は第1級だろう。
最後に、やはり音楽のハンス・ジマーだろう。ジマーはこの作品の為に『TENET/テネット』の参加を蹴って参入したのだという。オレは実はそれほどジマーに思い入れはないのだが、この『DUNE』における音楽は『ブレードランナー2049』におけるメタリックで無機的な轟音とはまた違う、女性ヴォイスを利用した有機的なサウンドを構築しており、映像に非常にエモーショナルな奥行きを与えることに成功していたと思う。
というわけでオレなりに『DUNE/デューン 砂の惑星』の見所をまとめてみた。というか見所だらけの作品であり、これをIMAXで観れたのは本当によかった。また、このIMAXにしても「大画面における高速なカット割り」は目を疲れさせ視聴を妨げる元であるとしてあえてゆったりとした編集にしたのだという。いつ公開されるのか、製作されるのかどうか全く分からない第2部ではあるが、首を長くして、そして大いに期待して待っていたい。
*1:ヴェルヌーヴ版映画作品ではクイサッツ・ハデラックと字幕が充てられているが小説版ではクイサッツ・ハデラッハと訳されている











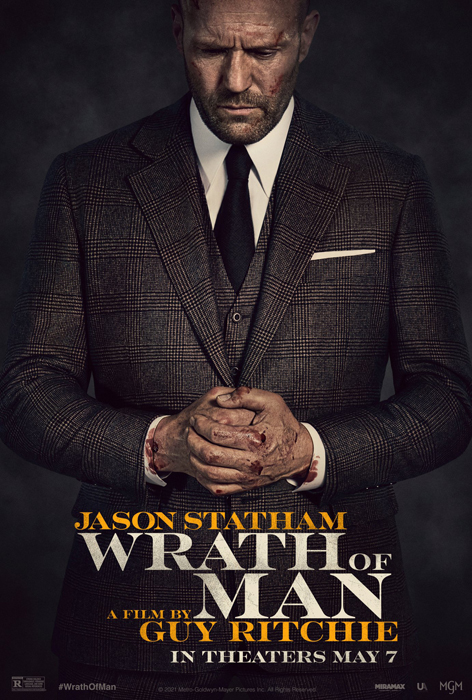
![ロック、ストック&トゥー・スモーキング・バレルズ [Blu-ray] ロック、ストック&トゥー・スモーキング・バレルズ [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51WJW2v99TS._SL500_.jpg)
![スナッチ [Blu-ray] スナッチ [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/5166fwhCosL._SL500_.jpg)
![リボルバー スペシャル・プライス [Blu-ray] リボルバー スペシャル・プライス [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51tIKhW5MIL._SL500_.jpg)
